スピードの重要性
「うちの子、サッカーを頑張ってるけど、もう少し足が速かったら…」
そんなふうに思ったことがある保護者の方は、
多いのではないでしょうか?
試合であと一歩のところで相手に追いつかれたり、抜け出しのタイミングが遅れたりすると、「スピードさえあれば…」と感じてしまうものです。
サッカーにおける“速さ”とは、単純な100m走のタイムではありません。
実際には「10m〜30mのダッシュ」や「一瞬の反応」「方向転換を含めた動き出しの鋭さ」など、総合的な“スピード感”が問われます。
特にジュニア世代では、
フィジカルがまだ発達途中であることもあり、
速さの差がプレー全体に与える影響は非常に大きくなります。
実際の私が教えるJクラブでも、
速い選手はピンチを切り開ける選手が多いです。
そのため、我々指導者としてもジュニア年代の選手には足を速くするトレーニングを行っていただきたいと思いますし、保護者の皆さんにも是非選手に寄り添っていただければと思っています。
■ 速さは才能じゃない。育てるもの
「足が速い子は生まれつき」
「うちの子は遅いから向いてないかも…」
そんなふうに考えてしまう保護者の方もいるかもしれません。
ですが、それは誤解です。
スピードは、才能ではなく
「育てることができる能力」です。
特に小学生〜中学生の時期は
「ゴールデンエイジ」と呼ばれ、
神経系や体の使い方がぐんぐん吸収されやすい年代。
この時期に“正しい動き方”を身につけていけば、スピードは大きく伸びます。
また、ゴールデンエイジとも呼ばれる所以は、この時期特有の神経系の発達と関係しています。
身体をとにかく速く動かせるようにするために、色々な遊びをさせる事。
特に鬼ごっこは足の速さ以外の要素も加わり、運動能力の向上に最適です。
実際にJクラブのジュニア年代では
トレーニングの一環として鬼ごっこを取り入れるところが多いです。
ジュニア年代にとって鬼ごっこは最強のトレーニングと私自身思っています。
■ スピードがあることで得られる3つのメリット
① 試合での武器になる
足が速いというだけで、
相手よりも先にボールに追いついたり、
守備でカバーしたりすることができます。
特にジュニア年代では、それだけで「目立つ存在」になりやすいです。
② 自信がつく
「自分は速い」という実感があると、
プレー全体が積極的になります。
速さは単なる運動能力ではなく、
“メンタル面での強みにもなり得る”のです。
③ ポジションの幅が広がる
スピードがあれば、
FWだけでなく・SBやウイング、
ボランチなどさまざまなポジションで起用される可能性が広がります。
■ 保護者にこそ知ってほしい「スピード育成」の本質
多くの保護者の方は、練習メニューや塾、
サッカースクールなどに目が行きがちです。
しかし本当に大切なのは、
・正しいフォームを意識させること
・日々の食事や睡眠、成長への理解
・親子で一緒に成長を楽しむこと
こうした「家庭での関わり方」です。
スピードは、たった数ヶ月で劇的に伸びることもあります。
特に、“良いサイクル”に入ったときの伸びしろはすごいものです。
だからこそ、今この記事を読んでくださっている保護者の方が、“育てる立場”としてできることを知っておくことには大きな意味があります。
このあと、30m走の平均タイムや家庭でできるトレーニング、プロ選手の事例などを交えながら、「スピードを伸ばすための全ステップ」をわかりやすく解説していきます。
ぜひ最後まで読み進めていただき、お子さんと一緒に“速さを武器にする育成”を楽しんでいきましょう。
学年別タイムの目安と意味
「速くなるにはまず目標を知ること」
これはスピード育成において基本中の基本です。
サッカー選手にとって重要な“30m走”は、
実際に多くのクラブやアカデミーで測定指標として用いられています。
ここでは、小学生〜高校生までの学年別平均タイムの目安と、その意味を解説します。
▶ 小学生(3〜6年生)の30m走目安
- 小学3〜4年生:5.5〜5.9秒
- 小学5〜6年生:5.0〜5.4秒
この年代では、発育や運動経験の差が非常に大きいため、タイムの幅も広くなります。
特に小学校高学年になると、5.0秒を切るような子どもも出てきて、「スピードタイプの選手」として注目されはじめます。
▶ 中学生(中1〜中3)の30m走目安
- 男子:4.7〜5.4秒
- 女子:5.0〜5.8秒
中学生になると、
体格や筋力がついてくることから、
30mのスピードに大きな差が出てきます。
4秒前半に入ってくると、
都道府県レベルでも通用するスピードといえるでしょう。
▶ 高校生(高1〜高3)の30m走目安
- 男子:4.2〜4.6秒
- 女子:4.6〜5.0秒
このレベルになると、単なる“足の速さ”だけでなく、加速スピードやストライド、反応速度といった複合的な能力が求められます。
高校生で4.1〜4.3秒を記録する選手は、
Jリーグや強豪大学でも
「速さの武器を持った選手」として高く評価されます。
▶ タイムは「順位」ではなく「成長の指標」
ここで一番大事なのは、
「タイムが早い=偉い」ではなく、
「伸びている=成長している」という視点で見てあげることです。
記録が0.2秒縮まっただけでも、
それは大きな進歩。努力の証です。
ぜひ、
- 定期的に測って記録する
- 前回との比較を楽しむ
- 親子で一緒に喜びを分かち合う
このような関わり方を心がけて、
数字を「自己肯定感の材料」として活用してみてください。
足が速い選手の特徴と分析
お子さんが目指すべき「速い選手」とは、
どんな選手でしょうか?
単純に“100m走が速い”というだけでは、
サッカーにおける「速さ」は語れません。
ここでは、実際にプロの世界で
“スピードを武器”にしている選手たちの特徴をもとに、
どのような走り方がサッカーに適しているのかを整理します。
▶ スピードが武器になるプロ選手たち
■ 三笘薫(ブライトン)
- ドリブル中の加速が異次元
- 姿勢が崩れないままトップスピードに乗れる
■ 伊東純也(スタッド・ランス)
- トップスピードに入るまでの時間が圧倒的に短い
- スプリント中でも冷静な判断ができる
■ 前田大然(セルティック)
- 「初速」が非常に速く、相手を一気に置き去りにする
- 守備でもスプリントを繰り返せる持久力も併せ持つ
▶ 共通する「サッカー型スピード」の特徴
これらの選手に共通する“速さの要素”をまとめてみましょう。
・低い重心と安定した姿勢 → 上半身がぶれず、加速にロスがない
・正確な腕振り → 腕をしっかり後方に振ることで脚の回転が速くなる
・前への力の伝え方がうまい → 地面を蹴るのではなく“押す”イメージで走っている
・判断力・予測力も含めた“認知的スピード” → ボールが来る前から動き出している
・走りながら周囲を見ている余裕がある → スピードだけでなく“プレーの質”が伴っている
▶ ジュニア年代で意識すべきこと
プロ選手のようなスプリント力をいきなり求める必要はありませんが、
以下のようなことを意識するだけでも、
走りは大きく変わります。
- 腕をしっかり後ろに振る
- 上半身をまっすぐ保つ
- 地面を蹴りすぎず、真下を押す
- 走る前に“どこに向かって加速するか”をイメージする
「足が速くなる=スプリント練習を頑張る」だけではなく、「走りの質を高める」意識を持つことで、サッカーで活きるスピードが育っていきます。
近年、プロのサッカー選手がオフシーズンに
陸上のコーチと走りのトレーニングをするのをSNSなどで見かけます。
足を速くすることはもちろん、
綺麗なフォームで走ることで怪我の予防や疲れにくい身体などを手に入れることが出来るからです。
そういったプロサッカー選手が口を揃えていうのが、
【小さい時からトレーニングしとけば良かった】
と。。。。
色々な動作パターンが身に付きやすいジュニア年代だからこそ、正しい動作を身につけることが重要と言えます。
次章では、そうした質を高めるために家庭でもできる具体的なトレーニングをご紹介します。
家庭でできるスピードトレーニングとフォーム改善
「スピードを伸ばしたいけれど、
クラブ練習以外に何をすればいいのかわからない」
そんな声にお応えして、
ここでは家庭や公園でもできる“具体的なスピードアップトレーニング”を紹介します。
毎日10分〜15分でも継続することで、
確実に走りの質は変わってきます。
▶ 自宅&公園でできる!スピードトレーニング5選
① ラダートレーニング(ステップ・素早さ・リズム)
- リズムよく足を動かすことで神経系を刺激
- 短い距離でできるため、狭いスペースでも可能
- 種類:1歩ずつ・2歩ずつ・横ステップ・前後ステップなど
👉 ポイント:腕の振りもセットで行うことでフォーム全体が良くなります
② バウンディング(バネ感・地面を押す感覚)
- 両脚交互に跳ねながら前進するトレーニング
- 地面を“蹴る”のではなく“押す”ことで反発力を高める
- 股関節の可動域や連動性も高まる
③ ハイニー(もも上げスキップ)
- 膝をしっかり高く上げ、体幹とリズム感を育てる
- 姿勢保持と「重心を前に乗せる」意識づけが可能
👉 ポイント:反動に頼らず、自分の力で膝を引き上げる
④ 10m×ダッシュ(フォームと加速)
- フォームを崩さずに“最初の3歩”に集中
- スタート時の姿勢や重心移動がカギ
- 回数は少なくてOK、3〜5本を丁寧に
⑤ 動画模倣トレーニング(視覚的な学習)
- 好きな選手のスプリントを見て真似してみる
- フォームやタイミングを自然と習得できる
- 親子で一緒に動画を見ながらチェックするのもおすすめ
▶ NGフォーム例とその改善アドバイス
| NGフォーム例 | 問題点 | 改善のヒント |
|---|---|---|
| 腕が真横に振れている | 上半身がブレて推進力が逃げる | 鏡や動画で後ろに引けているか確認 |
| 猫背や腰が落ちている | 重心が後ろにかかり加速が遅くなる | おへそを前に突き出す意識を持つ |
| 地面を叩くような走り | ブレーキ動作になっている | 地面を“押す”感覚を意識 |
保護者・選手におすすめの本
Jクラブでフィジカルを教えている私が、
サッカー選手を目指すなら手に取っていただきたい本を2冊ご紹介します。
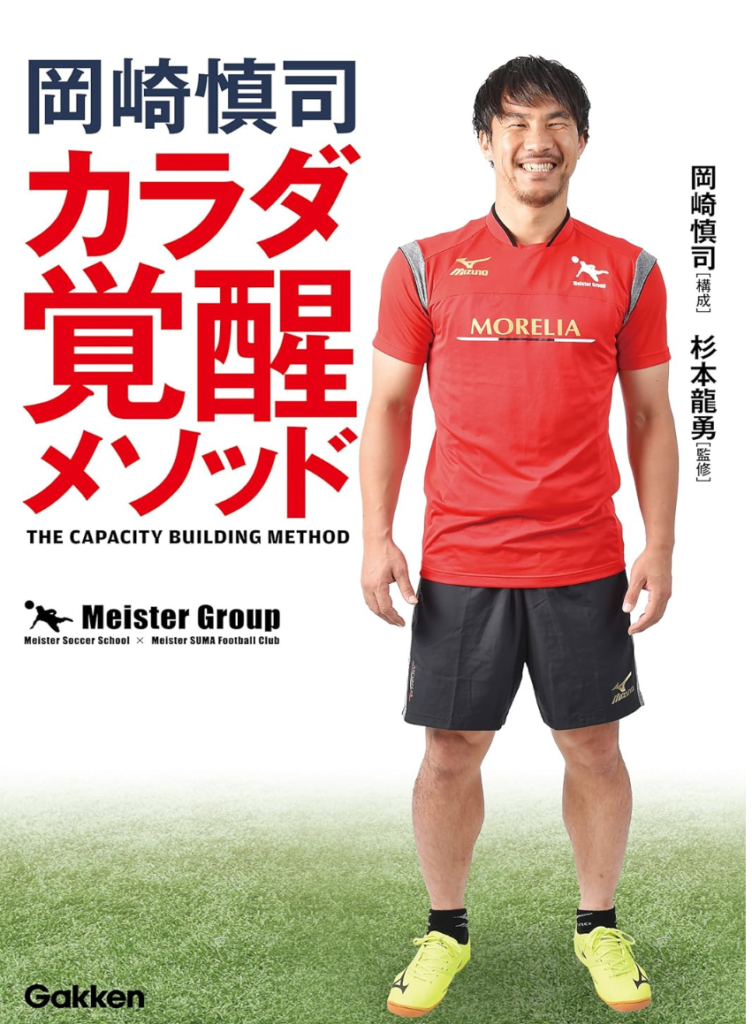
こちらは、元陸上選手の杉本龍勇さんが監修となっている本です。
こちらに書かれているトレーニングメニューは、日本代表の板倉滉選手や菅原由勢選手などもやっているので、サッカー選手を目指している選手には是非見てもらいたい本です!
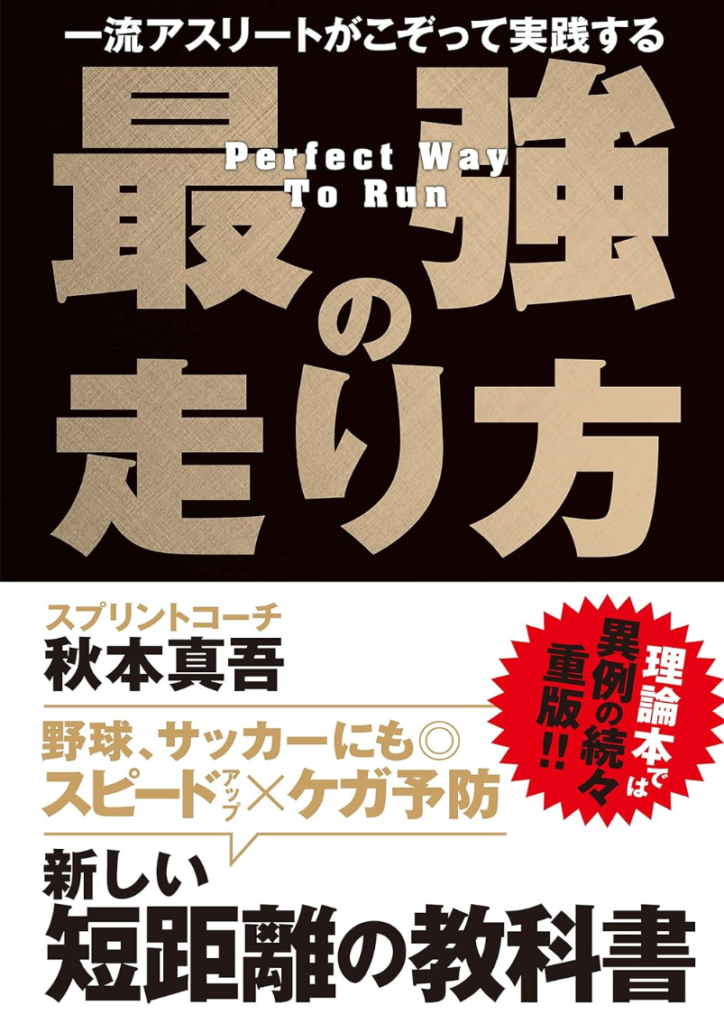
こちらは現在J2のいわきFCでスプリントコーチをしている秋本真吾さんが著者となっています。
サッカーのためのスプリントメニューやスポーツ選手との対談内容なども入っており、非常に理論的な本となっています。
▶ 保護者がサポートできる3つの視点
■ 1. 「見てあげる」だけで違う
子どもは「誰かが見てくれている」だけで頑張れます。
走っている姿を見守り、
「腕、良くなってきたね」など一言添えるだけで大きな励みになります。
■ 2. フォーム動画を一緒に見直す
スマホで撮った映像を、子どもと一緒に確認しましょう。
「このとき腕の振りが小さいね」
「ここで体が揺れてるね」などと共有することで、自分の動きを客観的に把握できるようになります。
■ 3. 無理させすぎない
「速くなってほしい」という気持ちが強すぎると、知らず知らずのうちに子どもを追い込んでしまうことも。
あくまで“楽しく継続”を大切に、
家庭内では“褒めて伸ばす”姿勢を意識してください。
▶ 継続のための工夫|「やらされ感」をなくすアイデア
- タイム記録をグラフにして壁に貼る
- 親子で競争形式にする(ママvsキッズ、パパvs兄弟)
- 週末は動画大会:「かっこいいフォーム選手権」など
「楽しい=続けたくなる」→結果的に伸びる、
という流れを意識しましょう。
次章では、スピードを支える
“成長期の身体との向き合い方”について詳しくお伝えします。
成長期の体との向き合い方
スピードを伸ばすうえで、
もうひとつ大切な視点が「成長期との付き合い方」です。
ジュニア期は身長が急に伸びたり、体のバランスが崩れたりと、日々身体が大きく変化していきます。
その変化に合わせたサポートがスピードの成長をスムーズにしてくれます。
▶ 骨が先に伸び、筋肉が追いつかない
小学校高学年〜中学生ごろは、
骨の成長スピードが一気に加速します。
それに対して、筋肉や腱、靭帯の成長はやや遅れがちです。
そのため、
- 可動域が狭くなる
- 柔軟性が低下する
- 筋肉が硬く感じる といった変化が起こりやすく、これが「走りにくさ」や「タイムの伸び悩み」につながることもあります。
※この現象をクラムジーと呼んだりします。
焦って無理な練習をさせるのではなく、
成長の“過渡期”として見守りつつ、
- ストレッチ
- 体幹トレーニング
- 正しいフォーム意識
といった“土台作り”に注力するのが効果的です。
▶ 成長痛(オスグッド・シーバー)への注意
成長期に多い代表的なケガが以下の2つです。
| 名前 | 主な症状・部位 |
|---|---|
| オスグッド病 | 膝の下(脛骨粗面)が出っ張って痛い |
| シーバー病 | かかとの骨(踵骨)が押すと痛い |
いずれも「成長中の骨」に“引っ張る力”が繰り返しかかることで発症します。
もしお子さんが、
- 「最近、膝が痛い」
- 「かかとを触ると嫌がる」 などと言い始めた場合は、すぐに休ませ、
無理をさせない判断が重要です。
冷やす(アイシング)や整形外科受診も検討しましょう。
▶ 睡眠と栄養も「走り」の一部
速く走るには、
ただ走るだけでなく“体づくり”が欠かせません。
その中でも睡眠と食事は、トレーニングと同じくらい大切です。
■ 睡眠のポイント
- 成長ホルモンは夜10時〜深夜2時に分泌される
- 小学生は9〜10時間、中学生でも8時間以上が理想
- 「寝る直前のスマホ・ゲーム」は控えるのが◎
■ 栄養のポイント(詳しくは後章で)
- タンパク質、鉄、カルシウムを意識
- 朝食で炭水化物+たんぱく質を摂る習慣を
▶ 成長の波を“乗り越える”ために
成長期には、一時的にスピードが伸び悩むことがあります。
でも、それは「止まった」のではなく
「変化している最中」。
その波をどう乗り越えるかで、スピードの質も変わってきます。
保護者の皆さんは、
- 子どもの体の声に耳を傾け
- 変化を受け止め
- 正しい知識で支える ことが、何よりも力になります。
次章では、スピードを支える“栄養と食事”について掘り下げていきます。
食事・栄養とスピードの関係
「走りが速くなる食事ってあるの?」
実は、あります。というよりも、
食事と栄養は“走りの土台”です。
どんなに良いトレーニングをしても、
身体を作る材料が不足していれば、筋肉は育ちませんし回復もうまくいかず、ケガのリスクも高まってしまいます。
ここでは、スピード向上のために意識したい
「3大栄養素」と、保護者として取り入れやすい食事の工夫をご紹介します。
▶ スピードアップに効果的な栄養素3選
① タンパク質(筋肉の材料)
- 肉、魚、卵、大豆製品に豊富
- 練習後や就寝前に摂ると吸収効率が良い
- 目安:体重×1.2〜1.5g/日(30kgなら約40g〜)
② 鉄分(酸素を運ぶ)
- レバー、赤身の肉、カツオ、あさり、ほうれん草など
- 成長期は貧血予防にも大切
- 吸収率を上げるビタミンC(みかん・野菜)も一緒に
③ 炭水化物(エネルギー源)
- ごはん、パン、麺、いも類など
- 練習前・後にしっかり摂取することでパフォーマンス向上
▶ 忙しい家庭でもできる工夫
「毎日完璧な食事なんて無理…」という保護者の方も多いと思います。
そんなときは、以下のような“シンプルな工夫”でも十分効果があります。
- おにぎり+ゆで卵 → 練習前後の定番補食に
- 朝食に納豆ごはん+バナナ → エネルギー+たんぱく質+ビタミン
- スープに豆腐や卵を入れるだけでもOK
- ヨーグルトや牛乳でカルシウム補給
▶ 補助食品の活用も選択肢に
- プロテイン(小学生用もあり)
- 鉄分入りゼリーや栄養バー
- ウィダーinゼリーなどの補食系ドリンク
使い方を間違えなければ、これらも十分に“育成サポート”として活躍してくれます。
👉 ポイントは「足りない分を補う」という考え方。
おすすめ→ジュニアプロテイン SAVAS
▶ 食事は“習慣”で差がつく
子どもは「何を食べるか」以上に「どんな食習慣があるか」で差がつきます。
- 朝ごはんを必ず食べる
- タンパク質を意識する
- 好き嫌いをなくすチャレンジ
こういった“小さな習慣”が積み重なることで、スピードアップに必要な土台がしっかりと整っていくのです。
次は、そうして育ってきたスピードを“最大限に活かす”ための、保護者の関わり方と声かけのコツについてお話しします。
保護者の関わり方とよくある質問
お子さんのスピードを伸ばすうえで、
保護者の関わり方はとても重要です。
ここでは「日常でできるサポート」「効果的な声かけ」「よくある保護者の質問」に分けてまとめました。
▶ 保護者にできるサポート5選
① タイムを記録して見える化
「ちょっと縮んだ!」が数字で見えると、
子どもはやる気になります。
- スマホのメモアプリやタイマーで管理
- 月ごとの記録をグラフにすると見やすい
② 動画を一緒にチェック
- スプリントを撮影して、子どもと一緒に見返す
- 「前より姿勢が良くなってるね」など具体的にフィードバック
③ “がんばり”に目を向ける
- タイムではなく「継続できた」「努力した」に注目
- 「0.1秒伸びても大きな進歩」だと伝える
④ 無理させすぎず、休ませる勇気も
- 疲れている時、違和感がある時は練習を休むことも大切
- 「今日はやめておこうか」と言ってもらえるだけで安心します
⑤ 応援者として寄り添う
- 一緒に走ってみる、見守る、声をかけるなど
- 「一緒に頑張ってくれる」存在であることが最大のサポート
▶ 効果的な声かけの例
- ×「ちゃんと走ってよ!」
- ◎「腕ふり良くなってきたね、あと少し!」
- ×「また負けたの?」
- ◎「タイム比べてみよう!昨日より速くなったよ」
- ×「なんで遅いの?」
- ◎「スタート、もうちょっと前傾でいけそうだね」
言い方ひとつで、子どもはやる気にもなるし、自信を失うこともあります。
“結果”よりも“プロセス”に目を向けた声かけが、子どもの成長を後押ししてくれます。
▶ よくある質問(Q&A)
Q. どれくらいで速くなりますか?
A. 1〜2ヶ月でも「フォームが変わった」「タイムが0.1〜0.3秒縮んだ」などの成果が見られることもあります。
Q. 毎日練習させた方がいい?
A. 毎日でなくてもOK。週2〜3回、10〜15分でも継続が効果を生みます。
Q. 足が遅いとサッカーに向いてない?
A. 全くそんなことはありません!
ポジショニングや判断力でカバーできる部分も多く、「走り」はあとからでも伸びるスキルです。
Q. 子どもがやりたがらない時は?
A. 無理にさせないで大丈夫です。
「今日は一緒に遊ぼう」くらいの感覚で、
軽い運動からスタートするのがおすすめ。
次はいよいよ最後のまとめパートです。 保護者としての「気づき」と「今後の育成の方向性」について振り返っていきましょう。
まとめ+今後の育成ビジョン
ここまで、
サッカーにおける「スピード」の重要性と、
家庭でできる育成方法をさまざまな角度から解説してきました。
ポイントを振り返ると、
・速さは“才能”ではなく“育てられる力”であること
・保護者の関わり方次第で、スピードは大きく伸びること
・食事や睡眠など、生活習慣そのものがパフォーマンスに影響すること
つまり、“走りを育てる”というのは、単に練習をさせることではなく、
お子さんの「からだ」と「こころ」を一緒に育てていく取り組み
でもあるのです。
速さが身につくことで、試合での自信がつき、
プレーに積極性が出て、チームでの存在感も増していきます。
そして、なにより「親に応援されて育った」という実感は、お子さんの大きな原動力になります。
これからも、お子さんと一緒に「スピード」を楽しく育てていきましょう!
今後は、
- 筋力トレーニング編
- スピードを活かすポジショニング編
- おすすめのジュニア向けシューズやアイテム なども記事にしていく予定です。
引き続き「ジュニアサッカー からだラボ」をよろしくお願いいたします!
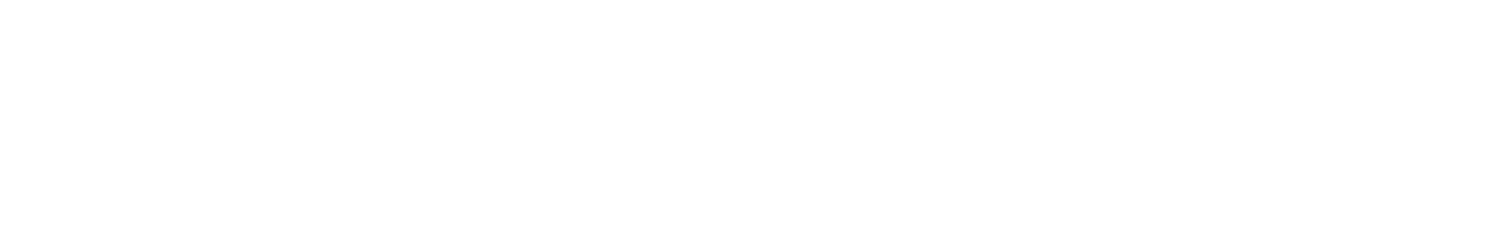





コメント