「背が高ければサッカーは有利ですか?」
保護者の方から最も多くいただく質問のひとつです。
今回はJリーグクラブでトレーナーとして働く私が育成期の最大の悩みでもある身長についてお伝えしていこうと思います。
たしかに、空中戦や競り合いでは“高さ”が頼もしい武器になります。
ただ、ここで誤解したくないのは
身長は万能のチートではなく、
選手が“争うフィールド”を変える要素だということ。
背が高いほど空で勝ちやすくなる一方、
地上ではアジリティ(俊敏性・切り返し)に不利が出やすい傾向もあります。
大切なのは「うちの子の身長は高い/低い」ではなく、“どのフィールドで勝つ設計にするか”の視点です。
センターバックやGKなら高さを生かす道があるし、ウィングや攻撃的MFなら低い重心を生かして狭い局面で勝てるかもしれません。
身長は才能の一部ですが、
勝敗を決めるのは“組み合わせ”と“使い方”。
本記事では、
身長のメリット・デメリットを整理しつつ、
身長×アジリティ×技術の最適解を、
育成年代の実情に合わせて分かりやすく解説します。
背伸びしてボールに届くのも大事。
でも、考え方の“背伸び”でもっと遠くへ届きます。
さあ、「結局、身長は高い方がいいのか?」
を一緒に整理していきましょう。
第1章:「背が高ければサッカーがうまくなる?」→その疑問、よく分かります。
サッカーをしている子どもを見ていて、
「うちの子、もう少し背が高ければ…」
と思ったこと、ありませんか?
試合を見ていても、
体格の良い子が相手を押しのけてボールをキープしたり、
コーナーキックで高く跳んでヘディングを決めたり――そんなシーンを見ると、
“やっぱり身長って大事なんじゃない?”と思うのは自然なことです。
実際に、年代別代表選手の平均身長は日本人平均より約6cm高いというデータがあります(ジュニアサッカーNEWS, 2020)。
U-15代表の平均身長は約170cm台前半、U-18では175cmを超える選手が多く、
成長期の段階でも「背が高い=選ばれやすい」傾向が見て取れます。
つまり、背が高い選手が上位カテゴリーに進みやすいのは事実です。
競り合いに強く、ボールを収めやすく、守備範囲も広い。
いわば、身長は“サッカー能力を支えるフレーム”のようなもの。
しかし、ここで注意したいのは――
「背が高ければすべてが解決する」わけではないということ。
なぜなら、サッカーは“多次元のスポーツ”だからです。
高さだけでなく、速さ、判断力、アジリティ、戦術理解、そしてメンタル。
どれか1つが極端に優れていても、
他の要素が噛み合わなければプレーは成立しません。
背の高さは確かに武器になりますが、
それは「多くの武器のうちの1つ」であって、
その選手がどんな戦場で戦うかを決める“特性”でもあるのです。
第2章:身長が高いと有利なシーンとは?「高さ」が武器になる瞬間
背が高い選手が有利になる場面は、
サッカーの中でたくさんあります。
それはもう、“高さ”という名の才能です。
一言でいえば、「空の支配者」になれること。
1. 空中戦の強さ ― コーナーやセットプレーで輝く
コーナーキックやフリーキックのとき、
ゴール前でひと際目立つのはやはり大柄な選手。
ヘディングの到達点が1cmでも高ければ、
勝負が決まることがあります。
実際、U-15年代のセンターバックやフォワードでは、175cmを超える選手が中心です(JFA育成データより)。
相手よりわずかに高い位置で触れる――それが“得点”か“失点”かの分かれ目になるのです。
2. 守備でのリーチ ― 「あと一歩」が届く安心感
センターバックやGKでは、
手足の長さがそのまま守備範囲に直結します。
GKのセーブ範囲を示す「カバレッジエリア」は、身長+腕長が重要。
180cmと190cmのGKでは、理論上横方向で約20cmの差が出るという報告もあります。
これはボール1個分――決定機を防ぐには十分すぎる差です。
3. 見た目の威圧感 ― 「相手を下がらせる」心理的効果
フィジカルコンタクトが多いサッカーでは、
“存在感”も戦術の一部です。
相手が無意識に距離を取ったり、競り合いを避けたりするケースもあります。
つまり身長は、技術や戦術を“引き立てる演出効果”にもなります。
4. チーム内での役割の幅が広がる
背の高い選手は、ポジション選択の自由度が高いです。
たとえば、中盤であっても守備時には空中戦のターゲットになれる。
攻撃時には、セットプレーで“もう一人のCF”にもなれる。
指導者から見ても「高さがある=オプションが増える」ことを意味します。
こうして見ると、身長は確かに“有利な素材”です。
特にセンターバック、GK、センターフォワードでは、
「高さをどう活かすか」で評価が変わると言っても過言ではありません。
ただし――
ここまでの話は“空中の世界”の話。
次章では、その真逆にある「地上の戦い」、
つまり身長が高いことで生まれるデメリットを見ていきましょう。
第3章:高ければ高いほど、アジリティは落ちる傾向にある
サッカーでは「背が高い=強い」というイメージがありますが、実は動きの面では逆の傾向もあります。
それは高いほど俊敏さ(アジリティ)は落ちやすい。
これ、単なる感覚ではなく、
ちゃんとした理由があります。
1. “物理の壁”――重心と慣性の関係
身長が高くなると、体全体の重心が高くなります。
重心が高いと、方向転換や切り返しで身体のバランスを保つのに時間がかかる。
しかも体重(=質量)も増えるため、動き出しに必要なエネルギーが大きくなるんです。
たとえば、同じ速さで方向転換するとき、
165cmの選手は軽い車、185cmの選手は大型トラックのようなもの。
どちらも曲がれるけれど、トラックの方が“ハンドルの切り返し”に時間がかかるんですね。
実際に私が教えていた選手の話ですが、彼は高身長で中学生にも関わらず、
すでに185センチを超えていました。
セットプレーでは特徴を生かせる一方で、
最大の課題はアジリティでした。
相手についていけない・ステップが踏めない。
簡単に裏を取られてしまう選手でした。(彼は主にディフェンダー)
2. 研究データが示す「背の高さとアジリティの関係」
筑波大学の運動生理学研究(※引用:体育科学研究誌 2019)でも、
同年代サッカー選手を比較したところ、
身長が高い選手ほど5m・10mスプリントで反応が遅れる傾向が報告されています。
一方で、30m以降では身長が高い選手の方がスピードが伸びる。
つまり――
「短距離(反応・切り返し)は小柄が有利」
「長距離(トップスピード)は高身長が有利」
この二つの特徴が、サッカーの“戦い方”を分ける要因になるのです。
3. アジリティ=才能ではなく「設計」
誤解しやすいのですが、
アジリティ(敏捷性)は生まれつきのものではありません。
トレーニング次第で“高身長でも動ける身体”は作れます。
たとえば、リバプールのフィルジル・ファン・ダイク(193cm)。
彼は大型DFでありながら、方向転換やスプリントでも世界トップクラス。
その理由は、股関節の可動性と体幹コントロールの高さにあります。
つまり、「高身長=鈍い」ではなく、
「高身長=より繊細なコントロールが必要」なのです。
4. 現場で感じる“アジリティ差”のリアル
私自身、Jリーグのトレーナーとして現場で見ていても、
身長が高い選手は「動き出し」「切り返し」「接触後の立ち上がり」でワンテンポ遅れることが多いです。
特にジュニア世代では、急に背が伸びて身体が追いつかず、“キレが落ちた”ように見える時期があります。
でもそれは、一時的な「成長痛」みたいなもの。
身体のサイズに神経系が追いつけば、またスムーズに動けるようになります。
保護者の方に伝えたいのは、
「今ちょっと動きが重そうでも、
焦らないで」ということ。
成長の途中でバランスを崩すのは、
“伸びしろ”の裏返しでもあるんです。
5. 実際に私が指導した選手の話
実際に私が教えていた選手の話ですが、
彼は高身長で中学生にも関わらず、
すでに185センチを超えていました。
セットプレーでは特徴を生かせる一方で、
最大の課題はアジリティでした。
相手についていけない・ステップが踏めない。
簡単に背後を取られてしまう選手でした。(彼は主にディフェンダー)
まさに木偶の坊状態。
ステップの踏み方から神経系のトレーニング。
体幹や筋力トレーニングを積み重ね、
アジリティはもちろん、スピードやジャンプ力などのフィジカル能力がどんどん向上していきました。
大事なのは、
自分の武器と課題を正確に把握すること。
そしてそのどちらにも目を向けて日々のトレーニングに励むことが、
サッカー選手として大成するのではないかと私は思います。
第4章:成長期に身長を「焦る」前に知ってほしいこと
ジュニア年代の保護者から最も多い相談のひとつが、
「同じ学年の子はもう170cmあるのに、うちの子はまだ150cm台で…」
という“成長差”の悩み。
ですが――ここに大きな誤解があります。
それは、「身長=才能」ではないということ。
1. 成長には“スパート期”がある
子どもの身長は、ある日を境にグッと伸びる時期があります。
これを「成長スパート期」と呼びます。
このタイミングは、個人差が非常に大きい。
JFAの発育データによると、
男子の平均的な成長スパートは 12〜13歳前後。
しかし、早い子では10歳台から始まり、遅い子では15歳を過ぎてから伸び始めることもあります。
つまり、「今小さい=これからも低い」ではないんです。
レイトマチュアラー(遅咲きタイプ)は、
中学〜高校で一気に10cm以上伸びるケースも多く、
むしろ身体が完成する頃にバランスの良いプレーができることもあります。
2. 遺伝は“60%”、残りは環境で変えられる
「身長は遺伝だから仕方ない」と思っていませんか?
たしかに、遺伝的要素は大きいです。
しかし近年の研究では、
身長の決定における遺伝の寄与率は約50〜70%とされています。
残りの30〜50%は、
- 栄養(タンパク質・カルシウム・ビタミンD)
- 睡眠(成長ホルモンの分泌時間帯)
- 運動(骨への適度な刺激)
といった後天的な要素で変わるのです。
特にサッカー選手は、トレーニング量が多いため消費カロリーが大きく、
「食べてるつもりで足りてない」ケースが本当に多い。
結果的に成長期の“材料”が足りず、身長の伸びが止まることもあります。
だからこそ、保護者の役割は
「栄養サポート」。
焦るよりも、“伸びる環境を整える”方がずっと効果的なんです。
3. 「今の身長」に一喜一憂しないで
サッカーでは、身長が高い子もいれば、低い子もいます。
でも、どちらにもチャンスがある。
たとえば、Jリーグでも170cm未満で大活躍する選手はたくさんいます。
川崎フロンターレ時代の中村憲剛選手(175cm)も、
小学生のころはチームでいちばん小柄だったと言われています。
彼が語っていた言葉が印象的です。
「身長で勝てないなら、考える速さで勝てばいい。」
身長は“能力の方向性”を決めるだけで、
“能力の上限”を決めるものではありません。
4. トレーナー目線での“焦り”へのアドバイス
私の現場でも、保護者の方が身長の話をするとき、
どうしても「比べてしまう」傾向があります。
でも、成長のタイミングは“その子の設計図”のようなもの。
焦ってサプリに走るより、
しっかり食べて・寝て・動く環境を整えることのほうがずっと確実です。
もし今、周りより小さくても、
「その分、低い姿勢からボールを奪える」
「素早くターンできる」
といった強みを生かせる時期でもあります。
“いま伸びていない=遅れている”ではなく、
“伸びる前の準備期間”なんです。
第5章:身長によって、争うフィールドが変わる
ここまで読んでいただいた方はもうお気づきかもしれません。
サッカーにおいて、**身長が高い・低いというのは「優劣」ではなく「特性」**です。
同じピッチに立っていても、戦っている“フィールド”が違う。
1. 高身長の選手は「空の戦士」
身長が高い選手は、空中戦で圧倒的な強さを発揮します。
- コーナーキックでの競り合い
- ゴール前でのクリア
- ロングボールの処理
これらはまさに“高さ”の勝負。
その一瞬の到達点の差が、勝敗を決めることもあります。
特にセンターバックやGKでは、
身長=評価基準になりやすい。
180cmを超える選手は、それだけで相手の心理にプレッシャーを与えます。
一方で、高身長選手は「切り返し」や「低いボール処理」に苦戦しやすい。
だからこそ、重心の安定・股関節の柔軟性を磨くトレーニングが必要になります。
彼らの戦場は“空”。
高さで勝負する、いわば空中の守護者です。
2. 低身長の選手は「地上の職人」
一方、身長が低めの選手は“地上戦のスペシャリスト”。
重心が低く、方向転換が速い。
小さなスペースでのプレーや、相手との距離感の作り方が抜群にうまい選手が多いです。
たとえば、イニエスタ(171cm)や久保建英選手(173cm)。
彼らは体格では劣っても、
- 俊敏なステップワーク
- 空間認知の高さ
- 相手を外す判断スピード
で、誰よりも“速く”プレーします。
彼らの戦場は“地上”。
ピッチの隙間で勝負し、視野と技術で相手を置き去りにするタイプです。
3. 戦うフィールドの違いを、親子で理解する
保護者の方にぜひ知っておいてほしいのは、
「身長が違えば、プレースタイルも違う」
という当たり前の事実です。
「うちの子は背が低いから…」と悩む前に、
「じゃあ、どんな戦場で勝つ子に育てよう?」
と考えてみてください。
たとえば、
| 身長タイプ | 得意なプレー傾向 | 向いているポジション | 鍛えたい能力 |
|---|---|---|---|
| 高め(175cm〜) | 空中戦・体のぶつかり合い | GK・CB・CF | 筋力・バランス・持久力 |
| 低め(〜170cm) | 俊敏性・ボールタッチ・視野 | MF・WG・SB | アジリティ・判断力・技術 |
このように「どの土俵で戦うか」が見えてくると、
焦りや劣等感は“戦略”に変わります。
4. チーム全体で見れば、“多様性”こそが武器
高さがある選手と、俊敏な選手。
この両者が混ざってこそ、チームは強くなります。
たとえば、
- 高身長のCBが空中戦で弾く
- 低身長のMFが素早く拾ってつなぐ
この連動こそが、現代サッカーの理想的な構造です。
どちらかが欠けても、チームのバランスは崩れる。
つまり、**身長の差は「チームの厚み」**なんです。
第6章:身長は“ラッキーな武器”、でも“それだけ”では勝てない
ここまで読んでくださった方は、
「結局、身長って“高ければいい”わけじゃないんだな」と
少し安心されたかもしれません。
そう、その通りです。
身長は“武器”にはなるけれど、“勝利の保証書”ではない。
1. 身長はスタート地点であって、ゴールではない
サッカーのピッチに立つと、
背の高い選手もいれば、小柄な選手もいます。
でも試合が始まれば、
「誰が高いか」より「誰が速く・正確に動けるか」が勝負を分けます。
高さで勝負する選手は、空中戦を制してチームを救う。
低さで勝負する選手は、地上戦でスルスルと相手を抜く。
どちらも“違うフィールドで主役”なんです。
2. 「身長を理由に諦める」ほどもったいないことはない
トレーナーとして現場にいると、
「うちの子は小さいから不利なんです…」という声をよく聞きます。
でも、実際にプロの現場を見ていると、
身長の低さを武器に変えた選手がたくさんいます。
例えば、横浜F・マリノスの西村拓真選手(170cm)。
スピード、ポジショニング、身体の入れ方、すべてが計算されていて、
体格差を感じさせないプレーをしています。
彼のように、
「自分の体格をどう活かすか」を理解した選手は、
どんな相手にも怯まずに戦える。
そしてその考え方こそ、ジュニア年代の選手にも伝えたい部分です。
3. “高いか低いか”より、“どう使うか”が本質
結局のところ、
身長とは“個性”であり、“戦略の出発点”です。
- 高ければ「空で勝つ」設計を
- 低ければ「地上で勝つ」設計を
そのために必要なのは、
「自分の身体を理解すること」なんです。
たとえ身長が思うように伸びなくても、
それを“弱点”と捉えずに“自分だけのスタイル”を磨くこと。
それが、育成年代で最も価値ある成長だと私は思います。
4. 保護者へのメッセージ
身長の話は、どうしても比べてしまうテーマです。
ですが、比べる対象を「他の子」ではなく
「昨日の自分」に変えてみてください。
たとえ1mmでも昨日より背が伸びた。
昨日より一歩速く動けた。
昨日より長くボールを追えた。
それだけで、立派な成長です。
焦らず、食事・睡眠・トレーニングという
“育つ3本柱”を支えてあげること。
それが、保護者にできる最高のサポートです。
🧠 最後に一言
「背伸びしても届かないボールはある。
でも、考え方を“背伸び”させれば、届く場所が広がる。」
身長は変えにくい。
でも、見方は変えられます。
そして、その“見方”を変えた選手ほど、最終的に一番遠くまで成長していくのです。
✅ まとめ
- 身長は確かに武器。ただし万能ではない。
- 高さを活かす選手もいれば、低さを武器にする選手もいる。
- 成長期は焦らず、今の身体を“どう使うか”を考える。
- 身長差は“才能の差”ではなく、“戦い方の差”。



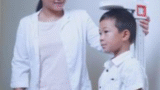

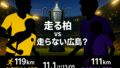
コメント